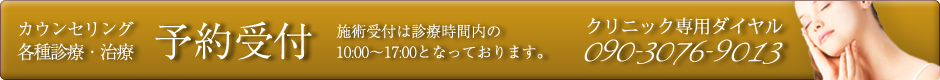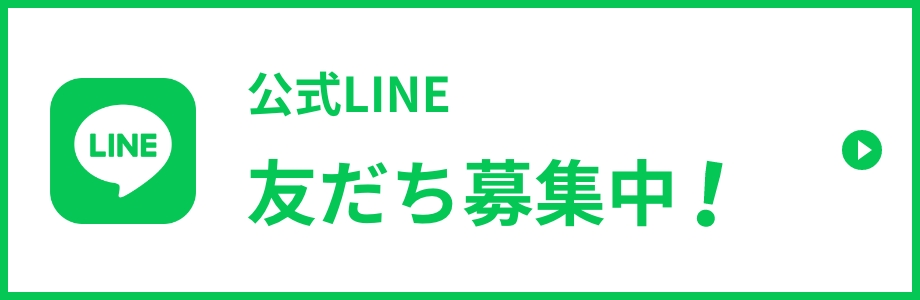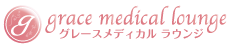ニキビ痕(ニキビ跡)の原因
ニキビ痕はその原因によっていくつかの種類がありますが、種類に関わらずどのニキビ痕も繰り返すニキビの炎症によって周囲の組織がダメージを受けている状態です。
ニキビの原因であるアクネ菌が肌で繁殖すると、退治するために白血球が毛穴へ運ばれて炎症が引き起こされます。
この際、白血球を効率よく毛穴へ運ぶために毛細血管が増えるため、肌が赤みを帯びます。
また、アクネ菌と白血球が戦うことで周囲の毛穴の組織が破壊され、コラーゲンが減少して凹んでしまいます。
その後、組織を修復するためにコラーゲンが過剰に産生され、かえって組織が硬く再生してしまうこともあります。
白血球に刺激されたメラノサイトからメラニン色素が過剰に分泌されるため、色素沈着を引き起こし黒ずみが残ることもあります。
このように、繰り返す炎症に伴う肌の組織変化をニキビ痕と言います。
ニキビ痕の種類
ニキビ痕は繰り返すニキビによる炎症に伴う組織変化であり、どのような組織変化を引き起こすかでいくつかの種類に分類されます。
- 赤みを帯びたニキビ痕
- 色素沈着を伴うニキビ痕
- クレーター状のニキビ痕
それぞれについて解説します。
①赤み(ざ瘡後紅斑)
ニキビ痕のひとつに、ざ瘡後紅斑と呼ばれる赤みを帯びたニキビ痕があります。
繰り返すにニキビによって炎症が引き起こると、ニキビを退治するための白血球をたくさん運べるように毛細血管が増生され、肌に赤みが生じます。
特に、強い炎症や繰り返す炎症が起こると毛細血管は次々に増生されていくため、赤みも強く残ってしまいます。
一度作られた毛細血管は基本的に無くならないため、赤みの自然治癒は期待できません。
もし肌に赤みができたら、放置せずに適切な治療を受けることをおすすめします。
また、赤みを気にして手で触るとさらに炎症が悪化し、赤みが増す可能性もあるため、手で触らないように気をつけましょう。
②色素沈着
ニキビ痕のひとつに、ざ瘡後色素沈着と呼ばれる色素沈着を伴うニキビ痕があります。
ニキビの炎症や化膿によって肌がダメージを受けると、白血球などによってメラノサイトが刺激されます。
活性化したメラノサイトによって大量のメラニン色素が分泌される一方で、ニキビができていた部分は皮膚のターンオーバーが乱れてしまうため、古い角質の排出がうまくいかず、肌にメラニン色素が残ってしまいます。
これによって、色素沈着を伴うニキビ痕が残ってしまうことがあります。
③クレーター
ニキビ痕のひとつに、クレーター状のニキビ痕があります。
皮膚は外側から順に表皮、真皮、皮下組織で構成されており、最も外側の表皮は病原菌や乾燥などから体を守るためのバリア機能を担っています。
しかし、肌のバリア機能が低下した状態で炎症が続くと、ニキビの原因となるアクネ菌がみるみる繁殖し、炎症が真皮や皮下組織にまで及ぶと、修復が難しいダメージを与えてしまうことがあります。
皮膚の奥深くでの炎症によって周囲のコラーゲンも破壊され、ニキビの治療後にクレーター状に皮膚が凹んでしまうニキビ跡が形成されます。
さらに、破壊された毛穴周辺の組織を修復する過程で過剰にコラーゲンが産生されると、固く出っ張った形で修復され、皮膚の表面では凹凸が目立つようになります。
炎症の範囲や程度によってクレーターの大きさや形は異なり、アイスピック型やボックス型などのさまざまな種類があります。
特にこめかみやおでこ、頬はクレーターができやすく、一度形成されると自然治癒は難しいため注意が必要です。
ニキビを予防するための対策
ニキビ痕は一度形成されると自然治癒は難しいため、炎症のある時に適切にニキビを治療する必要があります。
また、原因となるニキビを作らないためのセルフケアとして3つの予防法をご紹介します。
- 正しいスキンケア
- 正しい生活習慣
- ニキビができた時に肌を必要以上に触らない
それぞれについて解説します。
①正しいスキンケア
ニキビを予防するためには適切なスキンケアをおこないましょう。
ニキビの原因であるアクネ菌は皮脂を栄養にして繁殖するため、ニキビ予防のためには過剰な皮脂の増加を抑えるようなスキンケアの実践が重要です。
洗顔の際に肌を手で直接触ってしまうと炎症の原因となるため、洗顔料をたっぷりと泡だて、泡をクッションにするようにして肌を擦らないように優しく顔を洗いましょう。
また、洗い残しがないように、しっかりとぬるま湯ですすぐことも大切です。
すすいだ後の乾燥によって肌荒れすると新しいニキビの原因となるため、洗顔後は化粧水や乳液を使ってしっかりと保湿して、スキンケアを徹底しましょう。
特に乾燥が気になる方は高保湿のスキンケアアイテムを使用し、ニキビが気になる方はノンコメドジェニック対応のスキンケアアイテムを選ぶこともおすすめです。
②正しい生活習慣
ニキビを予防するためには正しい生活習慣を心がけましょう。
ニキビの発症は単一の原因では説明できないことも多く、ほとんどの場合は複数の日常生活における要因が複雑に影響して発症します。
そこで、正しい生活習慣を送って睡眠やストレス、食生活、便通、ホルモンバランスなどを整えることが大切です。
睡眠は肌の回復に必要なため、睡眠時間の確保や質のよい睡眠を心がけてください。
また、ストレスは女性ホルモンや自律神経のバランスが乱れる原因となり、肌トラブルを招きます。
ゆっくり入浴する・適度に運動する・自分なりのリラックス法を見つけるなどして、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
また、ニキビの予防にはバランスの良い食事摂取も欠かせません。
脂質や糖分・油分を抑え、野菜などの食物繊維やタンパク質を積極的に摂取することで皮脂の分泌を抑え、肌のターンオーバーを促すことが期待できます。
食生活が整えば腸内環境が整うことで便通も良好になり、ニキビができにくくなるでしょう。
③ニキビができた時に肌を必要以上に触らない
ニキビができた時には肌を必要以上に触らないようにしましょう。
ニキビが出来ると痛みや違和感でつい触りたくなってしまいますが、必要以上に肌を触らないことが大切です。
触ったことでニキビがつぶれてしまうと、正常な治癒過程を経ることができずニキビ痕の原因となります。
また、肌を触ると炎症が悪化する可能性があり、ニキビが繰り返されることでニキビ痕の原因となります。
そのほかにもマスクや枕の擦れ、頬杖なども刺激になるため注意が必要です。
新型コロナウイルス蔓延に伴いマスク着用が習慣化しましたが、中にはマスク着用によってニキビができやすくなったと感じている方もいます。
その場合、ウレタンや布素材のマスク、マスクと口の間に広めの空間ができる形状(ダイヤ型マスクなど)のマスクや空間を作るサポートアイテムは使用しないほうが良いでしょう。
これらのマスクは内側でこもりやすく、蒸れによってニキビが悪化する可能性があります。
そのため、内側が蒸れにくいプリーツ型の不織布マスクや、皮膚と擦れにくいマスクの使用を検討しましょう。
また、長い髪の毛が顔に触れると肌への刺激となるため、特に女性では注意が必要です。
前髪を短く切る、ピンで留める、髪を結ぶなどヘアスタイルを整えて、顔への刺激を低減できるように工夫しましょう。