運動をせずに痩せることは可能か

運動をせずに痩せる方法とは
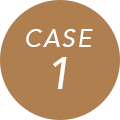 消費されるカロリーよりも摂取カロリーを少なくする
消費されるカロリーよりも摂取カロリーを少なくする
太ってしまう原因は、毎日の摂取カロリーが度を越えて多く、消費されることなく体の中に取り残されてしまうため、段々と脂肪という形でたまり体重が増加してしまうことです。体脂肪を減らすには、1日に必要なカロリーより摂取するカロリーを200〜300Kcal少なめにすると効果的だといわれています。低カロリーなメニューをバランスよく食べることを心がけ、1日3食、30品目の種類を少しずつ食べる食生活に改善していくとよいでしょう。ただし、過度のカロリー制限は体調不良の原因にもなり、注意が必要です。また、脂質は良質なものであれば積極的に摂取しても肥満の原因にはなりえず、常にバランスを考える必要があります。
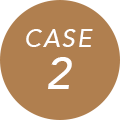 基礎代謝を上昇させる
基礎代謝を上昇させる
基礎代謝というのは人間が普段、運動しないで何もしていない状況でも消費されるエネルギーを意味します。基礎代謝がアップし盛んになることによって体脂肪が燃焼されると同時に、食事したものの蓄積を抑止する働きを獲得できます。運動をしなくてもカロリーを消費するためには、毎日の生活の中にちょっとした工夫を取り入れることが大切です。普段何気なく行っている家事や仕事で動きの一つ一つに対しての負荷を大きくすることでより多くのカロリーを消費することができます。階段があれば少し速足で昇り降りする、いつもより一歩を大きく意識しながら歩く、台所で家事をする間はつま先立ちや片足ずつ足の運動をしたり、お腹に力を入れたままにするなど、毎日やっていることに少し動きをプラスすることで身体に筋力がつき基礎代謝増加につなげることができます。
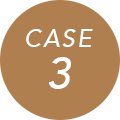 体脂肪を燃焼させる
体脂肪を燃焼させる
体脂肪というのは運動をしなければ減らせない、と考えている人が多いようでが、実は運動だけではやせることができません。運動だけに限らず、食事の食べ方やいつもの生活習慣を替えたり、工夫したりすることによってこの面倒な体脂肪をエネルギーへと変化させ、燃焼させることが可能なのです。また、22時から深夜の2時までは“睡眠のゴールデンタイム”と言われている時間帯で、早寝をすることで成長ホルモンが多く分泌され、脂肪を燃焼しやすい身体へと変えてくれます。早寝する人としない人では、消費カロリーにも差が出るとも言われているため、運動をせずに痩せたい人はこの早寝早起きの習慣を身につけるようにすると良いでしょう。
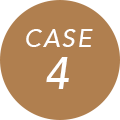 その他
その他
ストレスの増加は内臓脂肪が付きやすくなり、肥満の原因となります。代謝が悪い人やストレスなど抱えやすい人にはダイエットサプリもお勧めです。ダイエットサプリには、脂肪燃焼を助けるもの、糖質やカロリーをカットするもの、腸内環境を整えるものなど様々な種類があります。医師の指示に従いながら、許可が出ればサプリメントを試してみるのも良いでしょう。
運動をせずに痩せる方法とは
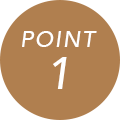 摂取カロリーを減らしてもタンパク質は減らさない
摂取カロリーを減らしてもタンパク質は減らさない
タンパク質は脂質が少なく、筋肉をつくるのに欠かせない栄養素です。摂取カロリーが減ってエネルギー不足になると、身体が自らエネルギーを作るため筋肉を分解し始めます。すると筋肉量が落ち基礎代謝が低下します。筋肉は基礎代謝の際、最も多くのエネルギーを消費するため、筋肉が減ると基礎代謝が低下して太りやすくなります。筋肉を維持するためタンパク質を減らさず、無理のない運動を心がけましょう。ただし、タンパク質のとりすぎは腸へ負荷がかかる可能性もあるため、便通も気をつけながらタンパク質を増やしましょう。
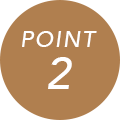 糖質と脂質どちらも摂取制限する
糖質と脂質どちらも摂取制限する
糖質は過剰摂取でカロリーオーバーに、脂質は過剰摂取で肥満の原因になるため目安摂取量を知っておきましょう。ただし良質な脂質はその限りではないと考えられます。
一般的には
糖質は「体重×1g」=「体重50kgなら1日50gまで」です。
脂質は「摂取カロリー×25%(30歳以上の目安)」=「1日1600kcalなら脂質は400kcalまで」です。
また、食べたものやカロリー、体重など記録するレコーディングダイエットは、食生活を見直すこともできますし、体重推移も確認することができるのでお勧めです。ただし常にバランスを考える必要があり、主治医と相談しながらダイエットをすすめてください。
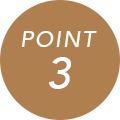 食事制限だけでなく、生活習慣まで見直す
食事制限だけでなく、生活習慣まで見直す
睡眠の時間が短かったり、睡眠の質が悪いと肥満になりやすく、とくにお腹の脂肪がつきやすくなると言われています。早寝早起きは、夜の空腹による間食を防いだり、自律神経のバランスを整える効果があります。結果、ホルモンバランスも良くなるので代謝が上がり、太りにくく痩せやすい身体に近づきます。睡眠不足やストレス、疲労の蓄積は太る原因です。これらを防ぐために、睡眠の質を上げる努力をしましょう。
◎運動する時間をわざわざ作り行動しなくても、毎日の生活の中で少しの工夫をする事で消費カロリーはどんどん増えていきます。日々少しの工夫でしっかり運動する事ができるので、小さな事でも続けられる工夫を見つけて継続していきましょう。


運動せずにやせることは可能です。運動は消費カロリーを増やす行動で、食事は摂取カロリーを増やす行動です。運動を行わないので消費カロリーが増えないため、摂取カロリーを抑えなければダイエットの成功にはならないということです。摂取カロリーより消費カロリーが少ない状態が続けば肥満につながります。そこで、摂取カロリーより消費カロリーを増やせば簡単に痩せられるのです。よって、体の痩せるメカニズムを考えると、食事のコントロール以上に効果的なダイエット法はなく、そこに必要な分の運動を足すという考え方が適切です。